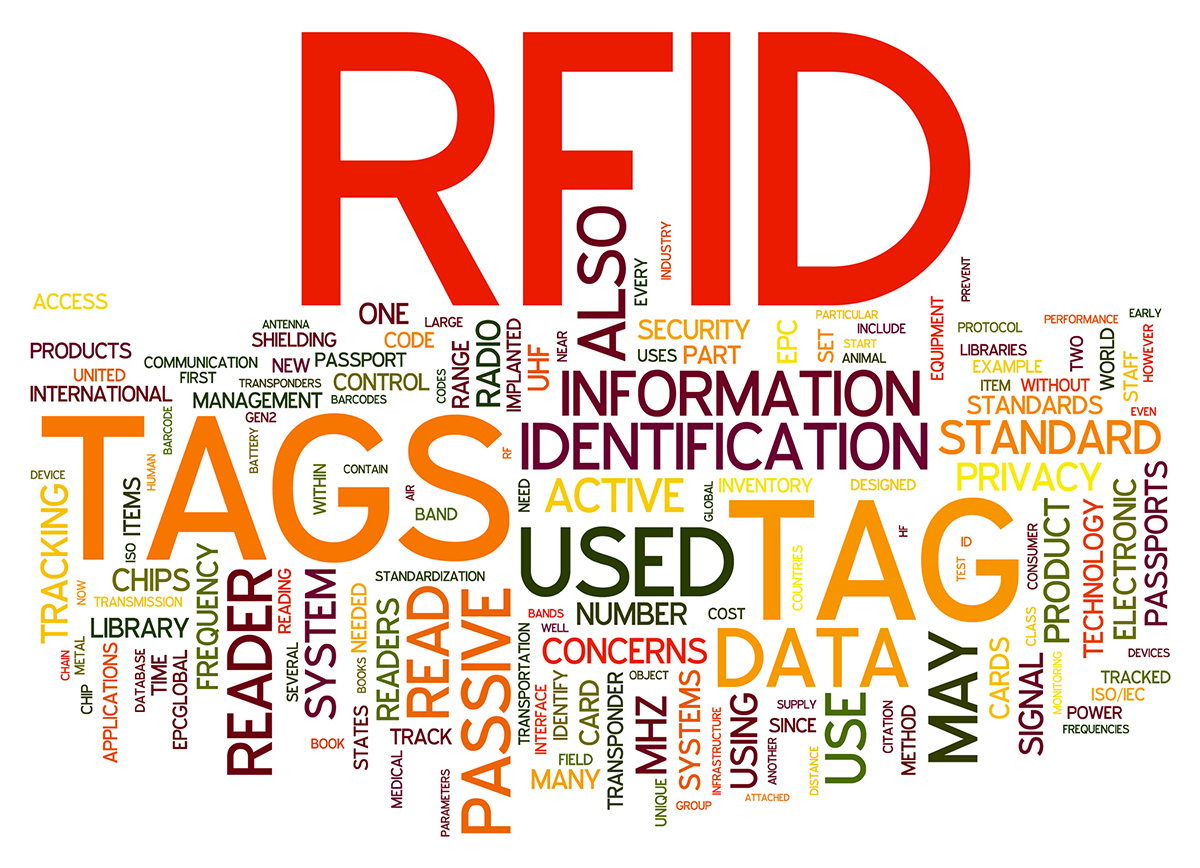
離れた距離から、まとめて読み取ることができるICタグ。
物品管理の場面では、管理したい物品にICタグを貼付することで、棚卸しや貸出しなどをシステム化し管理にかかる手間を削減することができます。
一方で、「物品に貼られているタグ」というと家電や化粧品などに付けられている万引き防止用の「防犯タグ」を思い浮かべる方もいるかもしれません。
では物品管理に利用される「ICタグ」と万引き防止用の「防犯タグ」にはどのような違いがあるのでしょうか?今回の記事では、この2種類のタグの違いについてご紹介します。
ICタグとは
ICタグは、電波などの無線で通信する機能を持ったタグのことで無線タグ、無線ICタグ、RFタグなどと呼ばれることもあります。
これらICタグと読み取り機器などを含めたシステム全体をRFID(Radio Frequency IDentification)と呼びます。つまりICタグとは「電波によって個体を認識することができるタグ」といえます。
防犯タグとは
では「防犯タグ」とはどのようなものなのでしょうか。
防犯タグは、ドラックストアや書店、家電量販店などで万引きを防止するために商品に取り付けられているタグのことです。
防犯タグは、その仕組みや形状から大きく4種類に分けることができます。
- ラベルタグ
- 加工タグ
- ハードタグ
- 自鳴式タグ
万引き防止システムは、こうしたタグに加えて
- タグを検知するゲートなどの検出装置
- ラベルを無効化する、もしくは取り外す解除器
の3要素が必要になります。
レジで精算する際にタグを無効化、もしくは取り外す処理を行います。処理がされないままゲートを通過するとアラームが鳴るため、万引きなどの不正持ち出しを防ぐことができます。
ICタグと防犯タグの違い
見た目が非常に似ているICタグと防犯タグ。
この2種類のタグの大きな違いは「個品管理をすることができるかどうか」です。
ICタグを使った管理の場合には、個々の物品を区別して管理することができます。
一方、防犯タグは1つ1つの商品を区別するような管理は行いません。例えば防犯タグとゲートを使った防犯システムの場合には「対応するタグがゲートを通過したらブザーが鳴る」仕組みです。そのため、「どの物品がゲートを通過したのか」までは分かりません。
(RFIDの技術を用いて商品管理 [棚卸し・在庫管理] と防犯対策 [ゲートでの検知・アラート発報] の2つを実現させるシステムもあります。)
ICタグと防犯タグは、見た目が似ているため混同していたという方もいらっしゃるかもしれませんね。
同じように見えるタグでも、それぞれのタグで適している運用方法や貼付物品が異なります。タグの持つ特長を理解して、物品管理に活かしていきましょう。
2017年4月には経済産業省から「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」が出され、2025年までに大手コンビニの全ての商品にICタグを取り付け、商品の個体管理を実現すると宣言されました。
また、経済産業省は2019年2月に「電子タグを用いた情報共有システムの実験」を実施しています。
ICタグで個体管理が可能になると、製造工程、物流工程、販売工程それぞれの状況や、現在どこにあるのか?といった所在が分かるようになります。そうすることで、万が一、商品に欠陥が判明しても追跡が可能になったり、販売状況から発注、製造を調整することができ食品ロスの解消に繋がったりと様々なメリットが想定されます。
コンビニの商品に限らず、手にするすべての商品に個体識別ができるICタグが付けられる日も近いかもしれませんね。
- 記載内容は、株式会社ネットレックスが作成したものを一部改変して転載したものです。
三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする
さまざまなサービスを展開しております
