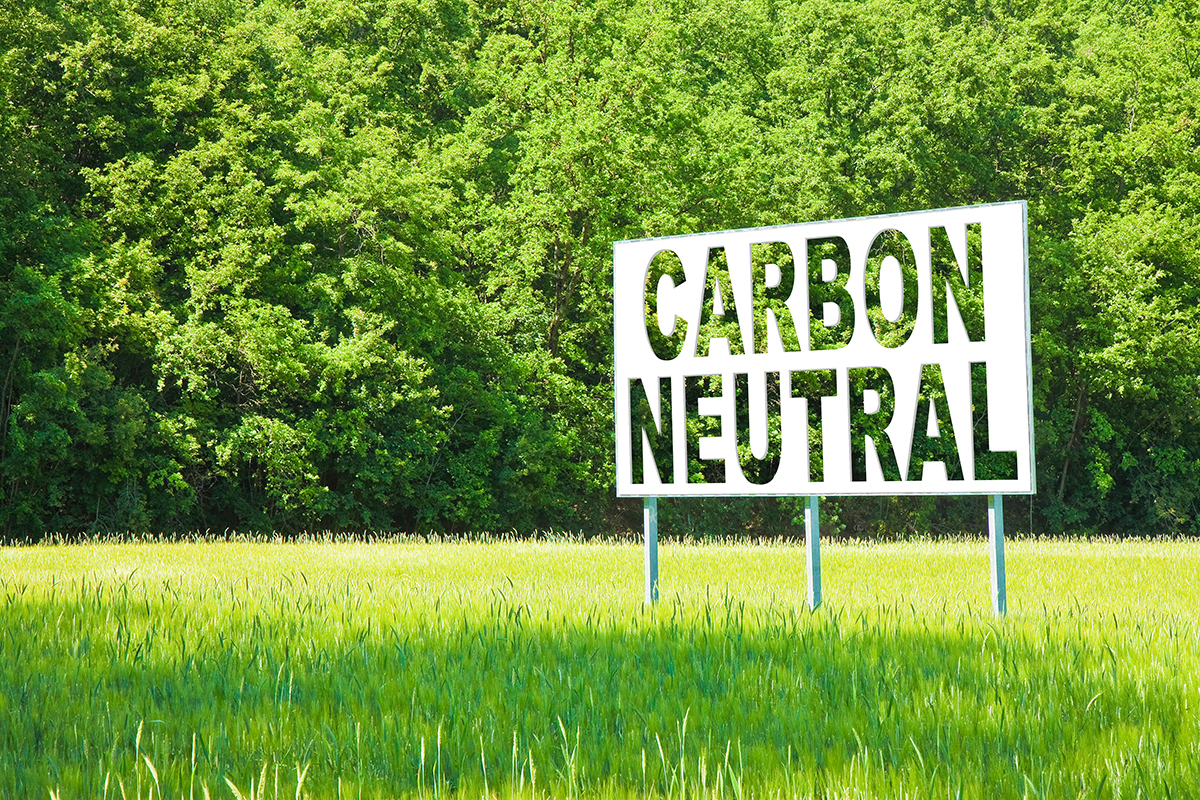
製造業の環境問題でよく耳にする言葉のひとつに、カーボンニュートラルがあります。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの「排出量」と「吸収量」を均衡させる、つまり差し引きゼロにすること。これは単に日本だけの課題ではなく、世界各国が取り決めたルールでもあります。このカーボンニュートラルを2050年に達成するため、大企業はもちろん、中堅・中小企業も真剣に脱炭素化に取り組むことが求められています。それは企業の社会的責任であり経営課題でもあるからです。船井総合研究所エネルギー支援部の藤堂大吉氏に、企業が脱炭素化に取り組まなかった場合のリスクや取り組むメリット、実行のポイントなどを聞きました。
目標は2050年カーボンニュートラル達成
どの企業も積極的に取り組む必要が
近年、世界中で気候変動に伴う災害が頻発しています。この地球規模の問題解決に向けて、2015年のパリ協定では、2020年以降の世界共通の長期目標として主に次のようなことが採択、合意されました(2016年11月発効)。
- 世界的な平均気温上昇を、工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(2℃目標)
- 今世紀の後半に、温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること
1997年の京都議定書が、気候変動に関する削減目標を当時の先進国だけが義務の対象だったのに対して、パリ協定は世界中の参加国を対象とし、世界中が合意したことが画期的でした。今では世界150以上の国・地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、様々な施策に取り組んでいます。
日本では2020年、当時の菅義偉首相が「我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言。翌年には「2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%削減の高みに向けて挑戦を続けていく」と表明しました。脱炭素社会の実現に向けて社会や産業構造を変革するGX(グリーントランスフォーメーション)も始動し、今後10年間の官民連携の投資のあり方やインフラ整備のためのロードマップ作成などが議論されていく予定です。
さて、このことは我々のビジネスにどんな影響を与えるのでしょうか。気候変動の一因である温室効果ガスは、経済活動や私たちの日常生活によって発生・排出されています。その積み重ねが気候変動を招いているのです。とりわけ経済活動において、「エネルギーを大量に使う大企業が頑張ればいい」と傍観していることは許されません。SDGs(持続可能な開発目標)推進と相まって、持続的な経済活動や成長戦略を実行するためには、企業規模に関係なく積極的に脱炭素化に取り組む必要があります。
政府は「2050年までに、CO2など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指す」と宣言(図:環境省「脱炭素ポータル」より)
進むサプライチェーン全体での排出量削減
脱炭素化に取り組まないのはリスクだらけ
では、企業がこの問題に無関心で脱炭素化に取り組まなかった場合、どんな影響やリスクが考えられるでしょうか。
1つめは「営業上のリスク」です。まず生産財においては、CO2排出量の削減をサプライチェーン全体で見る必要があります。例えば大手自動車メーカーに部品を納入している企業は、企業規模に関係なく脱炭素化に取り組まなければなりません。脱炭素化を推進しなければ、取引が打ち切られる可能性も否定できません。積極的に脱炭素化を進めている別の取引先に取って代わられるだけです。
またBtoCの消費財においては、サステナブルな商品であることが消費者に選んでもらえる重要な要素になりつつあります。「今やZ世代(1997〜2007年生まれ)やミレニアル世代(1981〜1996年生まれ)は、他の世代よりも環境配慮型商品を選ぶ人の割合が高いといわれています」(藤堂氏)。実際、ドイツに拠点を置くマーケティングリサーチ会社のGfKが2022年に米国内で行った調査によると、環境配慮訴求製品の購入経験はZ世代で62%、ミレニアル世代で67%に上り、それより上の世代の34〜47%と比較すると格段に高いことが分かります。日本においても、コンサルティング会社のファブリック(東京・目黒)が行った調査では、価格の許容度という観点で見ると「2倍の追加料金を払ってもいい」と答えた人はZ世代では20%と、他の世代(2〜8%)より突出しています。
一方、投資家や金融機関も、脱炭素化に積極的に取り組んでいる企業か否かを厳しく見るようになってきました。「将来的には、取り組みに消極的な企業は融資金利が高かったり、融資自体を受けにくくなったりする可能性も否定できません」(藤堂氏)。というのも、金融機関自体が国際社会や株主・投資家、監督官庁といったステークホルダーから、気候変動対応への期待や要請、評価などの対象となっているからです。こうした事情もあって、金融機関は顧客企業とのエンゲージメントを高めるために、脱炭素化のための融資や各種支援をしていく一方で、取り組みや情報開示を求める動きがますます活発になっていくと考えられます。
2つめが「コスト増によるリスク」です。代表的なものは、欧州で導入が進んでいるカーボンプライシング(炭素の価格付け)で、CO2排出量に応じて課税するという制度です。例えば、環境省が推す「炭素税」は、導入国の多くで1トンあたり2,000〜6,000円、スウェーデンでは同約16,000円とかなりの高水準になっており、日本でも導入を巡り経済界を巻き込んで議論が進められています。また、「排出量取引制度」は事業所ごとに排出量の上限が決められており、その上限を超えた場合は自治体が運営するサイトを通じて、上限まで達していない企業から必要な排出枠を買い取る仕組みです。例えば、東京都と埼玉県は燃料、電気等の使用量が原油換算で年間1,500kl以上の事業所(電力使用量換算では年間600万kWh換算以上)の施設を対象に、10年以上前からこの制度を導入しています。削減義務を履行できなければ、相応のコスト負担をしなければなりません。カーボンニュートラル達成のためにも、今後は他の自治体にも広がる可能性があります。
「3つめが『時流適応しないリスク』です。2030年、2050年の数値目標に向けて脱炭素化は世界的にスタンダードとなっています。そうした潮流に反して自社だけ取り組まないのは社会的に無責任であり、企業のブランド戦略としても得策ではありません。中長期的な経営・投資を考える際、脱炭素化は避けて通れません。まさに時代や社会の要請なのです。」(藤堂氏)
脱炭素化はまずCO2排出量の算定から
取引先開拓や採用面など多くのメリットも
脱炭素化はすぐに効果が出るわけではなく、あくまでも中長期的なスタンスが必要です。では、何からどのように着手すればいいのでしょうか。
「最初にやるべきことは、自社のCO2排出量の算定です。可視化しないことには削減施策も立てられません。ただ、算定だけで終わってしまうケースが多いのも事実です。大切なのは、経営トップが脱炭素化を社内外にコミットすること。そして、社長や担当役員、製造業の場合は工場長、ライン担当者、設備管理者などで構成する『カーボンニュートラル推進委員会』といったプロジェクトを立ち上げ、目標や実行計画の策定、そして運用へと進めていきます」(藤堂氏)
サプライチェーン排出量は事業者自らの排出だけでなく、上流から下流まで事業活動に関係するあらゆる排出量の合計を指す(図:環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」より)
また、昨今は原油高の影響もあり、電気代や燃料代の高騰が企業経営を圧迫させる状況にあります。そのような中での脱炭素化のための取り組みとしては、初期投資を抑えた設備投資、そして電気代や燃料代といった経費削減とCO2排出量の削減の両立が期待できるものから優先的に取り組んでいくべきしょう。また、「省エネはやり尽くした…」という声をよく耳にしますが、いざ現場へ伺うと施策の検討が甘かったり無駄が散見されたり、やりきれていないケースが多く、まだまだ取り組む余地があることが大半です。自社で推進しきれない場合は、他社と協業して進めていくことが大切です。
脱炭素化は本業とは別物として捉えられがちですが、本業に結び付くメリットもたくさん享受できます。例えば、新規取引先が増えることです。あるサプライチェーンでは、多数のサプライヤーによるCO2排出量の合計が全体の約9割を占めていたそうです。「自社でいくら努力してもCO2削減には限界がある」と気づき始めたのです。そのため、脱炭素化に積極的なサプライヤーを新たな取引先として求めています。つまり、脱炭素化を進めることでこれまで取引が叶わなかった大企業やグローバル企業との新たな関係を構築できる可能性があるということです。
また、自社商品を環境配慮型にして付加価値を上げることで、売り上げやシェアの向上にもつながります。そもそも環境問題への積極的な取り組みは、経営層のリーダーシップや行動力、そして社会的課題に全社で立ち向かう企業風土なくして成り立ちません。そうした企業姿勢に対して外部評価や企業イメージが向上すれば、新卒を中心とした採用面でも優位になります。
「最近、当社が注目しているのは『儲かる脱炭素経営』です。労力やコストの負担が増えるだけで“儲からない”のであれば、率先して取り組みませんからね。もっとも、儲かるというのは単純に売り上げや利益が増えるという意味ではありません。社会的義務として脱炭素化に取り組むのではなく、むしろ自発的、積極的に取り組んでいくことで新たな取引先・顧客の開拓や企業価値の向上が実現でき、そして次なる成長戦略を描くことができます。当社も、脱炭素化に取り組む意義や具体的な段取りなど様々な情報発信をして、さらなる啓発と理解を進めていくつもりです」(藤堂氏)
ルールや規制が厳しくなる一方で、国や自治体の脱炭素化推進のための補助金制度もたくさん導入されています。これまで述べてきたように、脱炭素化に取り組まないことのリスク、そして取り組むことによるビジネスチャンスをしっかりと整理して、カーボンニュートラルや脱炭素化という課題に早急に向き合っていく必要があります。
(取材・文:白子 聡/監修:船井総合研究所 第三経営支援部エネルギー支援部 脱炭素ビジネスグループ リーダー 藤堂大吉氏)
三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする
さまざまなサービスを展開しております
