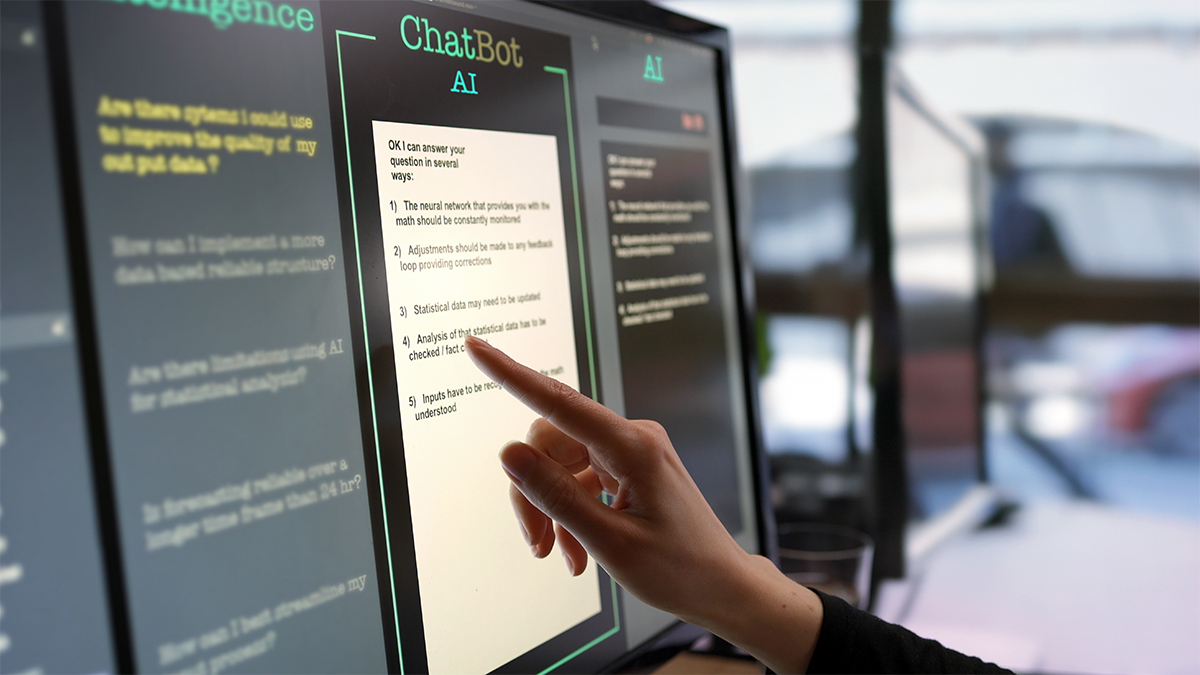
2023年になって、ChatGPTをはじめとする生成AI関連のニュースがとても多くなっています。IT系のネットニュースはもちろん、一般の新聞やテレビなどでも大きく取り上げられ、AIが私たちの生活や仕事に影響を及ぼすことをひしひしと感じている人もいるでしょう。特に、入力した問いかけに対して、対話するように文章を返してくる文章生成AIは、AIの活用の仕方を一変させるものと考えられています。オーダーメイド型AI「カスタムAI」の開発事業やコンサルティングを手掛けるAI企業のLaboro.AI(ラボロ エーアイ)で代表取締役CEOを務める椎橋徹夫氏に、これまでのAIと生成AIの違いや、今後のビジネスでの活用への期待についてお聞きしました。
■急速に広まる生成AI
出力情報量の増加と汎用性がカギ
ChatGPTに代表される生成AIの快進撃が止まりません。ChatGPTは米AI企業のOpenAIが開発した文章生成AIで、2022年11月に公開されてから一気に盛り上がりを見せました。こうした文章生成AIは、GoogleのBard、Meta(旧: Facebook)のLlamaなど、他の巨大企業も開発、提供を進めています。文章以外では、少し前から、入力されたテキストをもとに、自動で画像を生成してくれる、画像生成AIの分野が活発になっていました。
これらの生成AIはなぜ急速に活発になり、私たちの生活や仕事に入り込むようになってきたのでしょうか。生成AIを深掘りする前に、まずは、これまで使われてきたAIと、生成AIの違いを整理してみましょう。
Laboro.AI CEOの椎橋氏は次のように説明します。「これまでは、入力した文章が小説なのか科学書なのかを振り分けるような「分類タスク」や、文章内で多く使われている単語を抽出したりするなどの「認識タスク」が中心に取り組まれていました。これらは、学習したデータを基にして1つの解を導き出すという観点から言うと、入力の情報量よりも出力の情報量が少なくなると捉えられます。一方で、文章生成AIは、少ない入力情報に対して、単語の膨大な組み合わせの中から文章を作り出すことができるので、入力よりも出力の情報量が増えることが多いものです。つまり、出力の側の複雑度が格段に高くなっているのです」
画像分野でのAIの利用でも同様のことが言えます。すでに、画像を入力して「犬か猫か」「正常か異常があるか」といった識別、認識をするAIは多く使われています。これらは情報量の多い画像から単純な出力を得るものです。ところが画像生成AIでは、「テニスをする少年」などと短文の入力情報で指示をするだけで、指示に従った品質の高い写真やアニメのような画像を生成することができます。
他にも生成AIでは、これまでのAIとは異なる面があると椎橋氏は指摘します。それが、「汎用的なタスク」に応えられるようになったことです。「従来は、問題ごとに学習して特定のタスクに特化したAIを作る必要がありました。しかし、ChatGPTに代表される文章生成AIなどは、1つの自然言語モデルで、対話、要約、翻訳、検索などの幅広いタスクに対応しており、国語の問題も法律の問題もコンピュータープログラムの問題もサポートできるようになっています。このように汎化して使えるようになったことは応用面で大きな進歩です」
注目が高まる生成AIだけに、業界の動きは激しいものがあり、毎日のように国内外のニュースが飛び込んできます。
「生成AIが人間にかなり近い精度で自然言語やプログラムなどを作り出せるようになってきていることは事実です。AIやソフトウエアが人間と同じように言語を取り扱えるようになる日は、そう遠くない未来にやって来るかもしれません。その日が来ることを前提に長期的なビジネスや社会を今から考えておくべきでしょう」と椎橋氏は指摘します。
■広義の「翻訳」を担う生成AI
世の中の変化や可能性に注目
では、生成AIは実際のビジネスや産業でどのように使えるのでしょうか。椎橋氏は「今までとは異なる領域で利用が広がる」と指摘します。これまでは、製造業で言えば、製品の画像を認識して不良品を見つけたり、製造機器の補修時期を予測したりといった製造現場での用途が主流でした。「正常」「異常」といった出力をする従来型と異なり、生成AIは自然な言語で文章を生成したり、意図に沿ったプログラムを生成したりしてくれます。「製造業でも製造現場以外に、企画や設計などの上流部門で活用が進むことが期待されます。ものづくり以外では、広告のクリエーティブやコピーライティングを生成AIに任せることもできるでしょうし、コンテンツの企画構成などにも活用が期待されます」(椎橋氏)
さらに椎橋氏は、「情報の翻訳」という観点から生成AIの広がりを考えるとよいとアドバイスします。「例えば製造業の場合、製造機器の使いこなしに一定の技術が必要なことがあります。そのため、多くの場合で熟練技術者が経験と勘に頼った設定や操作を行っていますが、そうした熟練の技は暗黙知化され、言語化が難しいところがあります。これが、AIによって普段私たちが使っている言葉で機器の設定や操作ができるようになるかもしれません。今後は業界特有の手続きなども生成AIを使えば特別な知識がなくても自然言語で取り扱えるようになる可能性はあると思います。つまり、これまで専門的なスキル・ノウハウが必要だった作業を、日常的な感覚で実施できるようになる、言ってみれば『情報の翻訳』に長けているのが、生成AIの1つの特徴だと思うのです」
製造業や研究開発部門では、大量の外国語の専門的な論文などの情報を、日本語にしてさらに要約するといった使い方もあります。これも広い意味での情報の翻訳です。
一方で、生成AIで新しいビジネスが生まれてくるのかという問いに対して、椎橋氏は本質的な視野を持つことの重要性を訴えます。「例えば馬車の時代に新しく自動車が登場したとき、確かに人々に求められるビジネススキルやビジネスモデルの在り方は変化しましたが、移動という本質の提供価値は変わりませんでした。生成AIも、急に今までと全く異なる価値をもたらすことはないと思います。それよりも、AIが人力を代替することで生まれる変化や可能性に着目し、自社ビジネスを柔軟に適応させるための準備を進めておく必要があるでしょう」(椎橋氏)
■生成AIの活用はすでに始まっている
各社がビジネスの効率化に取り組む
変化や可能性に着目する動きはすでに始まっています。3メガバンクグループをはじめとした金融機関は生成AIの導入に舵を切っています。例えば三菱UFJフィナンシャル・グループは、ChatGPTを社内の書類作成や照会対応に活用して生産性向上に役立て、将来は独自AIの開発も視野に入れています。
製造・IT業界では、パナソニックグループがAIアシスタントサービス「PX-GPT」を導入し、技術職だけでなく製造・営業など様々な部門の社員の生産性向上と業務プロセスの進化に役立てようとしています。インターネット放送事業「ABEMA」やWeb広告事業を手がけるサイバーエージェントでも、デジタル広告の運用を効率化するためにChatGPTの活用を推進しています。
自治体など公共機関でも導入が進みます。全国に先駆けてChatGPTの活用を開始したのが、神奈川県横須賀市や茨城県つくば市で、文書の効率的な作成などに利用しています。横須賀市ではアンケートに回答した職員の約8割が「仕事の効率が上がる」「利用を継続したい」と好意的な意見を持っています。都道府県でも東京都がChatGPTをすべての部局で導入することを発表し、有識者会議の報告書の要約や、都が公表した資料に対する想定質問と回答の作成の参考にするなど用途を検討していくとしています。
生成AIは今後も技術的にも社会的にも、もまれて成長していきます。生成AIと共存しながら、人間がビジネスでさらに高い価値を生み出し、快適な暮らしができるような将来について、今から備えておくことが大切なのです。
(取材・文:岩元直久/監修:Laboro.AI 代表取締役CEO 椎橋徹夫氏)
